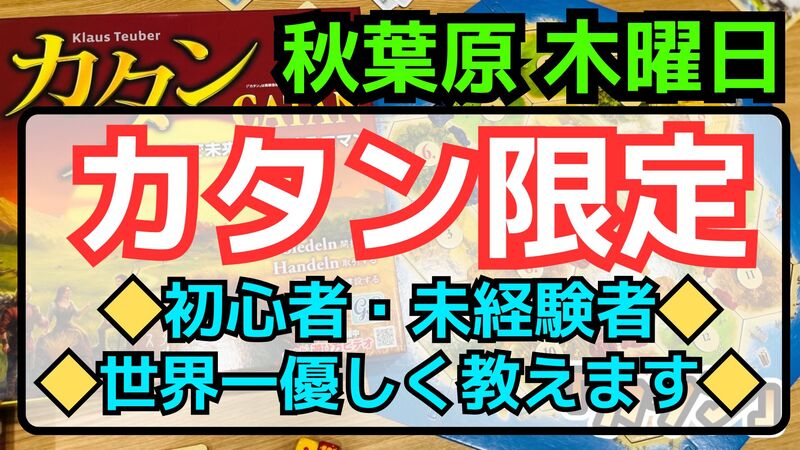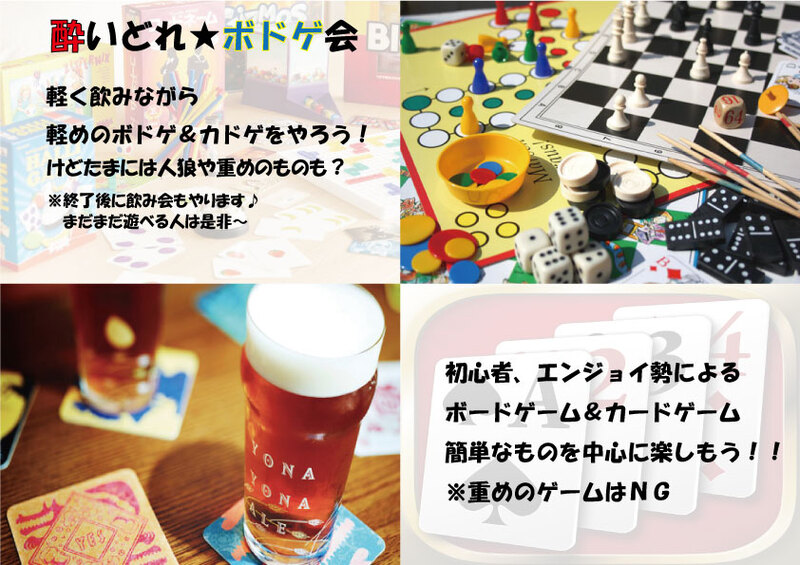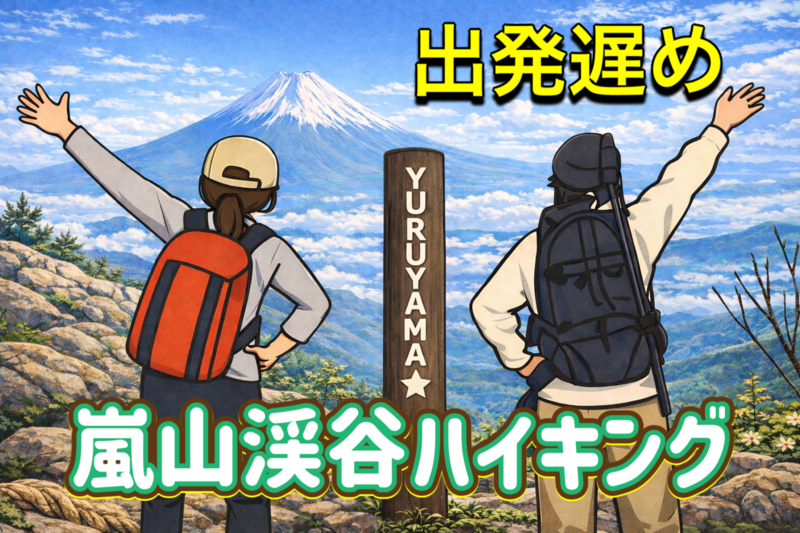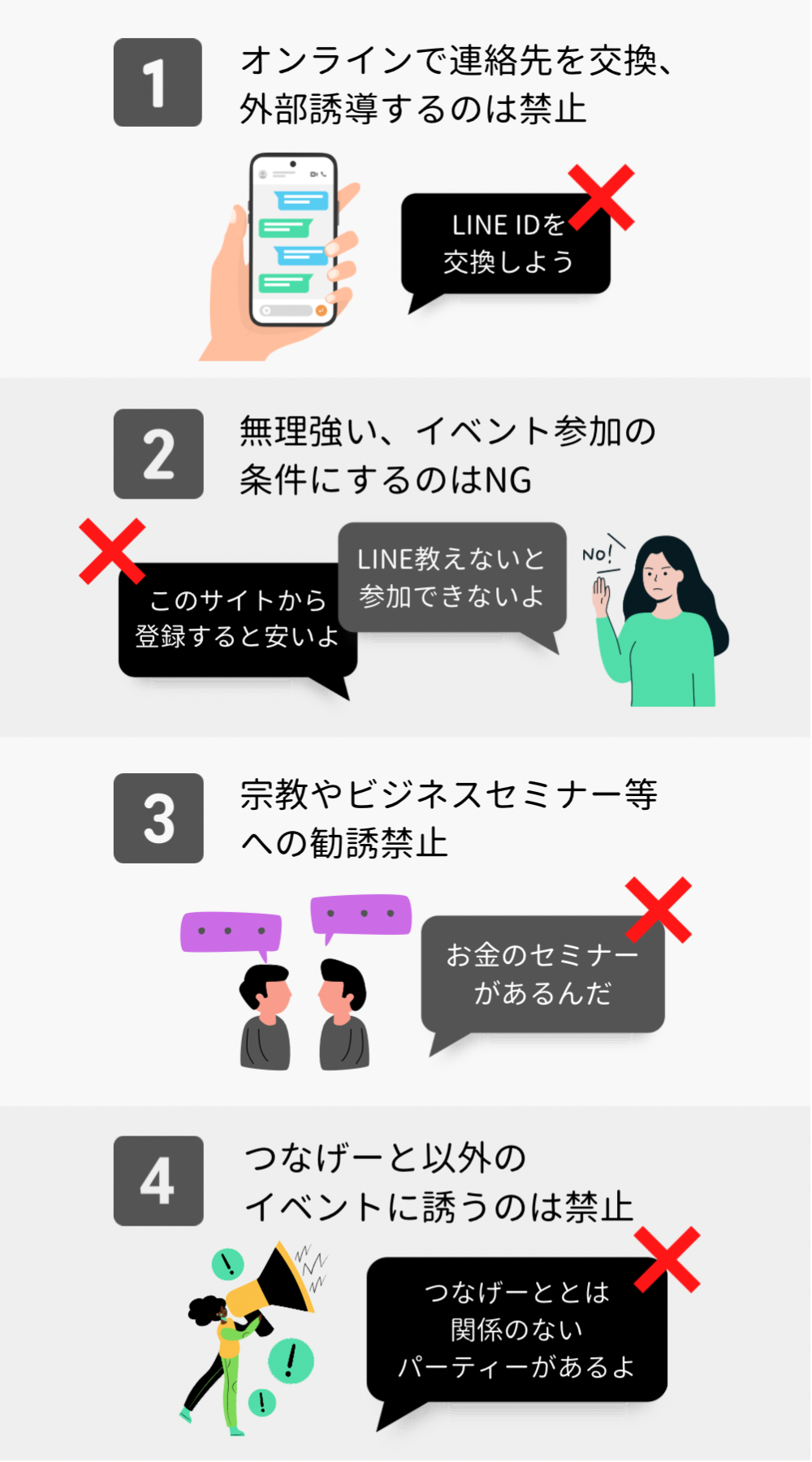誰もが一度は作成した事があるであろう俳句ですが、俳句が生まれ文学として確立した歴史はあまり知られていないのではないでしょうか。
本イベントでは俳句の師と称される松尾芭蕉が暮らした深川ゆかりの地を巡り、俳句文化の歩みを学びます🐸
【スケジュール】
11:30 森下駅 集合
松尾芭蕉の生涯と俳句史について予習(1時間〜1時間半)
※カフェ併設のレンタルスペースにて勉強会
↓
〈芭蕉記念館 〉
※芭蕉ゆかりの品や資料を展示
↓
〈芭蕉庵史跡展望庭園〉
※芭蕉庵(芭蕉宅)の跡地。芭蕉像あり
↓
〈臨川寺〉
※芭蕉が師である仏頂禅師に学びに通った寺
↓
〈採茶庵跡〉
※芭蕉が「奥の細道」の出立直前まで住んだ門人(弟子)の別荘跡
↓
〈清澄庭園〉
※「古池や 蛙飛び込む 水の音」句碑あり
自由散策 → 解散(15:30解散予定)
↓
《希望者のみ》
〈深川江戸資料館〉
※江戸末期の深川町の町並みを実物大で再現していて見応えあり(16:30解散予定)
※ 勉強会併設カフェには軽食の販売有り。
ランチしながら聴講。食べ物持込みも可。
🌸概要
芭蕉以前、俳句は「ふざけたもの」として蔑視されていましたが、松尾芭蕉の数々の試みによって次第に俳句は文学としての地位を確立し、芭蕉の死後は門人たちによって普及発展していきました。
松尾芭蕉が文学にまで高めた俳諧は【蕉風】と呼ばれ、のちに近代俳句の師である高濱虚子は『俳句は即ち芭蕉の文学であるといって差支ない』とまで評しています。
今回は俳句史としては前半部にあたる松尾芭蕉の生涯と「蕉風」を継いだ弟子たちの時代(1600年代〜1800年代)を中心に、俳句文化の歴史的経過をお話しようと思います。
その後は芭蕉が人生最後の旅となる「奥の細道」出立直前まで暮らした深川ゆかりの地を辿ります♫
誰もが一度は作成した事があるであろう俳句ですが、俳句が生まれ文学として確立した歴史はあまり知られていないのではないでしょうか。
本イベントでは俳句の師と称される松尾芭蕉が暮らした深川ゆかりの地を巡り、俳句文化の歩みを学びます🐸
【スケジュール】
11:30 森下駅 集合
松尾芭蕉の生涯と俳句史について予習(1時間〜1時間半)
※カフェ併設のレンタルスペースにて勉強会
↓
〈芭蕉記念館 〉
※芭蕉ゆかりの品や資料を展示
↓
〈芭蕉庵史跡展望庭園〉
※芭蕉庵(芭蕉宅)の跡地。芭蕉像あり
↓
〈臨川寺〉
※芭蕉が師である仏頂禅師に学びに通った寺
↓
〈採茶庵跡〉
※芭蕉が「奥の細道」の出立直前まで住んだ門人(弟子)の別荘跡
↓
〈清澄庭園〉
※「古池や 蛙飛び込む 水の音」句碑あり
自由散策 → 解散(15:30解散予定)
↓
《希望者のみ》
〈深川江戸資料館〉
※江戸末期の深川町の町並みを実物大で再現していて見応えあり(16:30解散予定)
※ 勉強会併設カフェには軽食の販売有り。
ランチしながら聴講可能。食べ物持込みも可。
🌸概要
芭蕉以前、俳句は「ふざけたもの」として蔑視されていましたが、松尾芭蕉の数々の試みによって次第に俳句は文学としての地位を確立し、芭蕉の死後は門人たちによって普及発展していきました。
松尾芭蕉が文学にまで高めた俳諧は【蕉風】と呼ばれ、のちに近代俳句の師である高濱虚子は『俳句は即ち芭蕉の文学であるといって差支ない』とまで評しています。
今回は俳句史としては前半部にあたる松尾芭蕉の生涯と「蕉風」を継いだ弟子たちの時代(1600年代〜1800年代)を中心に、俳句文化の歴史的経過をお話しようと思います。
その後は芭蕉が人生最後の旅となる「奥の細道」出立直前まで暮らした深川ゆかりの地を辿ります♫






 4人
4人